第一部の振り返り
前回、私たちは1980年のBruce Springsteenのアルバム「The River」を通じて、当時のアメリカ労働者階級が直面していた現実を見てきた。
B面1曲目の「Hungry Heart」に登場する「行き先を知らない川」から、B面最後の「The River」の「枯れた川」へ—この旅は、製造業の衰退、夢の喪失、希望の枯渇を象徴していた。
しかし当時は、少なくとも敵が見えていた。工場の経営者、グローバル化、システム—何と戦えばいいかが明確で、労働組合という武器があり、Springsteenのような代弁者が存在した。
では、45年が経った2025年の今、状況はどう変わったのだろうか?
働く場所そのものが消えた
最も皮肉で深刻な変化がこれだ。
1980年、「The River」の主人公は工場で働けていた。仕事はきつく、給料は十分ではなく、夢を諦めざるを得なかったが、それでも仕事はあった。苦悩は「仕事の中での不満足」だった。
しかし今、その工場自体が消えている。
ラストベルト(錆びた工業地帯)と呼ばれる地域では、かつて何千人も雇用していた工場が廃墟となった。デトロイト、ピッツバーグ、クリーブランド—これらの都市は、栄光の製造業時代の残骸を抱えている。
現代の若者は「つらい仕事に耐える」以前に、「安定した仕事を見つける」こと自体が困難になっている。
より深刻な点
1980年代の工場労働には、重要な意味があった:
- 学歴がなくても中産階級の生活を築ける道だった
- 住宅ローンを組み、家族を養い、子供を大学に送れた
- コミュニティの一員として、尊厳を持って働けた
今はサービス業や不安定なギグワーカーとしての雇用が増え、同じ生活水準を維持することが極めて難しい。地域社会全体が崩壊し、「川で涼む」ような共同体の場所さえ失われつつある。
Springsteenが歌った「苦しいけれど存在する労働」から、**「労働の機会そのものの喪失」**へ。これは社会構造の根本的な変化だ。
AI時代—ホワイトカラーも例外ではない
そして今、歴史的な大転換期が訪れている。今度は知識労働者の番だ。
三段階の労働の変容
第一段階(1980年代〜): ブルーカラーの喪失
- Springsteenが歌った製造業の衰退
- グローバル化と自動化で工場労働が消滅
第二段階(2010年代〜): 中間層ホワイトカラーの圧迫
- データ入力、事務処理などルーティン業務の自動化
- アウトソーシングの拡大
第三段階(2020年代〜現在): 高度知識労働への浸食
- AIによる執筆、プログラミング、デザイン、分析業務
- かつて「安全」とされた専門職(弁護士、会計士、エンジニア)も影響下に
皮肉な逆転
1980年代、大学教育は「工場労働から逃れる道」だった。親たちは子供に「勉強しないと工場で働くことになる」と言った。
しかし今:
- 高額な学費を払って大学を出ても、安定した仕事の保証はない
- ホワイトカラーの仕事もAIに代替される可能性がある
- 学生ローンという新たな「鎖」が若者を縛る
かつて「逃れる先」だった場所が、今や同じように不安定になっている。
見えない敵—現代の本質的な苦しさ
ここに、現代特有の最も深刻な問題がある。
1980年代は、苦悩の対象が明確だった。しかし今は何に対して苦しんでいるのかが見えにくい。
1980年代: 集団的な苦悩
- 「俺たちは工場で搾取されている」
- 「グローバル化が仕事を奪った」
- 「経営者が悪い」
→ 敵が明確で、仲間と共有できる苦しみ
現代: 個人的な失敗感
- 「なぜ自分はうまくいかないのか」
- 「もっと頑張らないといけない」
- 「選択を間違えたのかもしれない」
→ 敵が不明確で、孤立した苦しみ
何が見えないのか?
現代の若者が直面している問題:
- システムの複雑さ: グローバル化?AI?プラットフォーム経済?アルゴリズム?誰に抗議すればいい?
- 自己責任論: 「頑張れば報われる」と言われるが、何をどう頑張ればいいのか不明瞭
- 比較の地獄: SNSで「成功している他人」が常に見え、比較と焦燥感が生まれる
- 選択肢のパラドックス: 「選択肢が多い」ことが逆にプレッシャーになる
- 内面化された敵: 敵は外部ではなく、自分の中の不安や焦り
連帯の困難
敵が見えないから:
- 怒りをぶつける先がない
- 連帯しにくい(みんなバラバラに苦しんでいる)
- 「自分が悪い」と内面化してしまう
- ストライキや労働組合が機能しにくい
かつての川は「逃げ場」だった。でも今は、物理的な場所も精神的な逃げ場も見つけにくく、「何から逃げているのか」さえ定義できない漠然とした不安がある。
冷戦構造との類似—誰と交渉すればいいのか
この構造の変化は、実は国際政治の変化とも驚くほど似ている。
冷戦時代(〜1991年): 明確な二極構造
- アメリカ vs ソ連
- 資本主義 vs 共産主義
- NATO vs ワルシャワ条約機構
敵も味方も交渉相手も明確だった。
キューバ危機のような危機が起きても、ホットラインで首脳同士が話せば何とかなる可能性があった。核の脅威は恐ろしかったが、少なくとも誰と話せばいいかは分かっていた。
冷戦後〜現在: 断片化した世界
- テロ組織、サイバー攻撃、地域紛争
- 国家 vs 非国家主体
- イデオロギーではなく、宗教、民族、経済的利害の複雑な絡み合い
「誰と交渉すればいいのか」が不明。
イスラム国やサイバー攻撃者に電話する「ホットライン」は存在しない。敵は分散し、断片化し、見えなくなった。
労働問題も同じ構造
1980年代の労働問題:
- 労働者 vs 工場経営者/資本家
- 労働組合が交渉相手として機能
- ストライキという明確な武器
- 団体交渉で条件改善の可能性
現代の労働問題:
- プラットフォーム経済、アルゴリズム、AI、グローバル・サプライチェーン
- 誰に抗議すればいい?Google?Amazon?株主?それともシステム全体?
- ギグワーカーは団結しにくく、交渉力がない
- アルゴリズムが決定するので、人間の交渉相手がいない
共通する無力感
「戦う相手が見えない」= 無力感の増大
- 冷戦時代: 反戦運動、軍縮交渉に意味があった
- 現在: 何に反対し、誰と交渉すればいいのか分からない
- 1980年代: ストライキや労働運動で変化の可能性
- 現在: システムが複雑すぎて、何をしても変わらない気がする
この構造的な類似は偶然ではない。明確な対立から、複雑で見えにくい対立への移行—これは現代社会全体を覆う変化なのだ。
「Hungry Heart」の現代的意味
ここで、改めてSpringsteenの歌詞に戻ろう。
「Hungry Heart(飢えた心)」という言葉が、今、新しい意味を持ち始めている。
1980年当時の「Hungry Heart」
- 充足されない欲求
- 家族や安定した生活では満たされない何か
- しかし、何を求めているかは分かっていた
- 自由、冒険、逃避—明確な対象があった
2025年の「Hungry Heart」
- 何を求めているかも分からないまま飢えている心
- 漠然とした不安と焦燥感
- 「これじゃない」という感覚だけがある
- でも「何が正解か」は見えない
かつてのhungry heartは、明確な飢餓感だった。今のhungry heartは、何に飢えているかさえ分からない渇望だ。
「行き先を知らない川」の深化
“Like a river that don’t know where it’s flowing”
この歌詞は、45年前よりもさらに切実な意味を持つようになった。
- 1980年: 行き先を見失った若者たち
- 2025年: そもそも行き先が存在するのかさえ分からない
川は流れているのか?
流れているとしたら、どこへ?
そして、たどり着く場所はあるのか?
音楽が鳴り続ける意味
それでも、私たちは今日もライブで「Hungry Heart」を大合唱する。
楽しく身体を揺らしながら、家族を捨てて去る男の歌を歌う。
笑顔で、仲間と肩を組みながら、喪失と絶望の物語を共有する。
この矛盾こそが、音楽の持つ力だ。
音楽がもたらすもの
- カタルシス: 日常では言えない本音や葛藤を、音楽を通じて解放する
- 連帯: 「これ、実はヤバい内容だよね」という共通認識が一体感を生む
- 承認: 自分だけじゃない、みんな同じhungry heartを抱えている
- 一時的な救い: 重いものを軽やかに届ける音楽の魔法
見えない敵と戦い、何を求めているかも分からず、孤立した苦しみを抱える現代において、音楽は数少ない「川」なのかもしれない。
一時的でも、そこで人は自由を感じ、つながりを感じ、生きている実感を得る。
結び—川は今も流れているのか
Springsteenが「The River」で描いた川は枯れていた。
45年後の今、その川はどうなっているだろうか?
おそらく、川はまだそこにある。
形を変え、場所を変え、意味を変えながら—でも確かに流れている。
文字通り川に向かう人は減ったかもしれない。
工場も、労働組合も、明確な敵も、もうないかもしれない。
しかし、「hungry heart」を抱える人間は今も存在する。
違うのは、その飢えの性質だ:
- 1980年: 何に飢えているかは分かっていた
- 2025年: 何に飢えているかも分からない
そして私たちは、その飢えを抱えたまま、
行き先を知らない川のように、
ただ流され続けている。
それでも
それでも、音楽は鳴り続ける。
Springsteenの歌は、45年経った今も、人々の心に響く。
なぜなら、彼が歌ったのは1980年の物語であると同時に、人間の普遍的な物語だからだ。
- 失われる夢
- 見えない敵
- 枯れゆく希望
- それでも生きる人々
- そして、どこかに川を求め続ける心
川はまだ流れている。
私たちが音楽を聴き、歌い、つながり続ける限り。
重いものを軽やかに届ける音楽の魔法は、今も生きている。
そして、その魔法こそが、現代の私たちにとっての「川」なのかもしれない。
二部作を終えて
1980年、Bruce Springsteenは「行き先を知らない川」と「枯れた川」を歌った。
45年後の私たちは、さらに複雑で見えにくい世界に生きている。
ブルーカラーからホワイトカラーへ、明確な敵から見えない敵へ、集団の苦悩から孤立した不安へ。
しかし本質は変わっていない。
人は常に、川を求めている。
自由を感じる場所、つながりを感じる瞬間、生きている実感を得られる時間—それが川だ。
そして音楽は、時代を超えて、その川へと私たちを連れて行ってくれる。
たとえそれが一時的なものであっても。
たとえライブが終われば現実が待っていても。
音楽が鳴り続ける限り、川は枯れない。
Bruce Springsteen “Hungry Heart” (1980)
Bruce Springsteen “The River” (1980)
from the album “The River”
【第一部】行き先を知らない川—Springsteenが1980年に見ていたものも併せてお読みください。

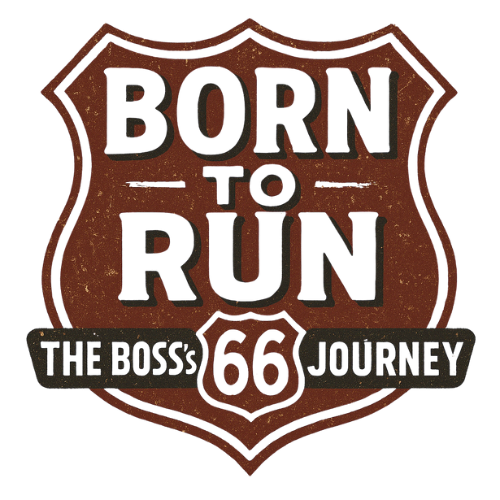

コメント